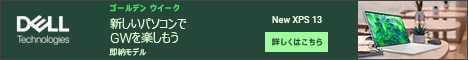|
MENU 筑波山 つくば近隣ガイド 茨城県 広告 |
白雲橋コース
筑波山中腹の筑波山神社拝殿と女体山山頂を結ぶ登山道。筑波山を代表する登山道。
登山道の前半は眺望は無く、森林浴を楽しむコース。
後半は弁慶七戻りに始まる筑波山の奇岩を楽しめる。さらに頂上付近は眺望がある場所も多い。
ただ最後は急傾斜の岩場になる。
また、後半はつつじケ丘方面から登るおたつ石コースが合流する。
案内板も多く、登山者も多いため、道に迷うことはまずなく、初心者でも安心して登れるコースのひとつ。 最も迷いやすいのはスタート地点である筑波山神社境内。白雲橋コースに関する案内がほとんど無く、一度一般道へ出るなど、最初に来た場合は分かりにくい。 標高約280mから標高約877mまで、標高差は約600m。 登山道を登山口から順番に写真で紹介、登山道全線の状況が分かるようにした。 トイレは、筑波山神社、ロープウエイ女体山駅にある。登山口までの交通は、公共交通機関では、筑波山シャトルバスで筑波山神社前下車。 自動車の場合はつくば市営駐車場(第1から第4駐車場)が便利。 筑波山のほかのコースの全線ガイド(写真ガイド)は 御幸ケ原コース(筑波山神社拝殿と御幸ケ原を結ぶコース)、 おたつ石コース(つつじケ丘から白雲橋コースに接続、女体山山頂に至るコース)、 迎場コース(つつじケ丘から白雲橋コースに接続し、筑波山神社拝殿へ至るコース)、 筑波高原キャンプ場コース(筑波高原キャンプ場と女体山山頂を結ぶコース)、 深峰歩道(旧ユースホステルコース、旧ユースホステルから御幸ケ原を結ぶ、筑波山の登山コース中最も短いコース)、 湯袋峠沢コース(湯袋峠と仙郷林道を結ぶコース、筑波高原キャンプ場コース、深峰歩道に接続)。 
筑波山神社拝殿前から登山道方向を望む。拝殿に向かって右手方向に進む 

突き当りを左へ。巨樹の方向へ進む。この辺には案内が何も無い(左)、 狭いところを通って下の道へ(右) 

左にあるのは愛宕神社。鳥居の右側を通って階段を降りる(左)、 愛宕神社の先に八幡神社、その前の階段。ここを降りる。そして左へ(右) 
橋を渡る。渡りきって右へ。そしてすぐに左へ。橋の名前は白雲橋 

ここを直進。右に案内標。左に「是より女体山」の石碑。ここから案内がある(左)、 突き当たりを左へ。左に案内標(右) 

ここを登る。かなり急傾斜な一般道(左)、 登山道入口鳥居。実質的に登山道はここからスタート(右) 

鳥居すぐは、かなり狭く感じる空間。特に夏場は両脇から草が生い茂る(左)、 徐々に幅が広がる(右) 

かなり広がる(左)、 道幅は狭いが、空間は広い(右) 
登山道左側、すぐ脇で崖崩れが起きている 

白雲橋コース前半の登山道のスタンダード。この状況が酒迎場分岐まで続く(左)、 自然豊かな道を歩く(右) 

B−01地点。女体山頂まで2400m、つつじケ丘まで1790m、筑波山神社から270m(左)、 この辺は傾斜も緩く、歩きやすい遊歩道といった感じの道(右) 

緑も深くなり、鬱蒼とした場所もある(左)、 樹木の太さもまちまちで、森の奥深さを感じる(右) 
この付近からは巨樹、そして大きな岩も多くなる 

森林浴を十分に楽しめる。新緑の時期には、特に気持ちのいい空間だ(左)、 整備された歩きやすい登山道(右) 

やや傾斜が出てくる(左)、 苔生した大きな岩が登山道の雰囲気をよくしている(右) 
酒迎場分岐。左が白雲橋コースで女体山頂方面、右が迎場コースでつつじケ丘へ向かう 

分岐を過ぎると、整備された登山道から自然の登山道へ(左)、 しばらくは自然石と木の根の登山道が続く(右) 

この付近で標高約350m(左)、 登山道が狭くなってくる(右) 
B−02地点 

再び広々とした登山道(左)、 石が多いものの基本は土で、雨で濡れると滑りやすいので注意が必要(右) 
正面に白蛇弁天。コースは弁天前で右へ 

弁天前からコースを見る。傾斜がややきつくなる(左)、 部分的に平らな場所はあるものの、傾斜は結構ある(右) 
自然石の登山道のなかを進む。この付近から自然石が大量にある場所が多くなる 

傾斜もかなり急、かつ足場が悪い場所も(左)、 自然石が階段状に並べられている(右) 

傾斜が急にかつ道幅が急に狭くなる(左)、 白雲橋コースでは、森林のなかで開けた場所が数カ所かる(右) 

やや狭くなる自然石の階段(左)、 再び開けた場所。自然石がかなり多くある(右) 
苔むした自然石の階段が雰囲気のある登山道となっている 

ゴツゴツとした自然石が雑然とある登山道(左)、 自然石の隙間が多い場所。木の根が多く張り出している(右) 

自然石と木の根が登山道をつくっている(左)、 木の階段。傾斜はかなり急な場所(右) 

自然石の階段と木の階段の連続(左)、 B−03地点。女体山頂まで1800m、筑波山神社から870m(右) 

この付近も急な傾斜が続く(左)、 木の根がむき出しになっているところも多い(右) 

一部階段が整備されている部分もある(左)、 きちんと階段があり歩きやすい(右) 

すぐ近くはほとんど自然のままの道(左)、 この付近も自然のまま(右) 
かなり開けた場所。自然石と木の階段が一部にある 

この付近は木の階段(左)、 大量の自然石の中を進む(右) 

傾斜はかなり急(左)、 右に曲がる(右) 

自然石が多い登山道(左)、 右カーブ(右) 

自然のままの登山道(左)、石の階段の先に舞台のような場所(右) 

石の階段で右カーブ(左)、 登山道左側の岩の上に稲荷神社(右) 

女体山頂まで1.6km、筑波山神社まで1.1km(左)、 右側が崖、道も細い(右) 

多くの自然石を乗り越えていく(左)、 B−04地点。女体山頂まで1500m、筑波山神社から1170m(右) 

この付近から開けた空間が広がる(左)、 開けた空間ながら傾斜は結構ある(右) 

大きな石の間を抜けていく(左)、 大きな倒木もある(右) 
コースのほぼ中間地点はこの付近 

ほとんど自然状態の道(左)、 かなり急な上り(右) 

大きな自然石の階段(左)、左カーブ(右) 

開けた場所。傾斜はあまりきつくない(左)、 急に狭くなった場所(右) 
この先に広場のように開けた場所。休憩ポイント 

休憩ポイント(左)、この付近から聖天神社分岐まで部分的なアップダウンはあるものの、標高のゲインはほとんど無い(右) 

ほぼ平らな登山道(左)、この付近も平らな登山道が続く(右) 
B−05地点。女体山頂まで1200m、筑波山神社から1470m 

引き続き平らで見通しのいい場所が続く(左)、 この付近も若干の盛り上がりはあるがほぼ平ら(右) 

登山道の真ん中に樹木(左)、 登山道に岩や樹木(右) 

急に細くなった登山道。土のため滑りやすいので注意(左)、 右に直角に曲がる(右) 

曲がった先も狭い道(左)、 狭く歩きにくい道が続く(右) 

狭いが平らな道(左)、 部分的に小さな石の階段(右) 
岩が道を塞いでいる。ここは左右に迂回路 

完全に大きな岩が道を塞いでいる場所も。かなりの段差を乗り越えていく(左)、 この付近は石の間を抜け、石で出来た段差を乗り越える場所も(右) 
女体山頂まで1.0km、つつじケ丘まで1.2km、筑波山神社から1.7km 

小さな石の階段(左)、この付近は両側から植物が生い茂り、道幅を狭くしている(右) 
石が登山道を塞いでいるようにも見える 

狭い登山道。左カーブ(左)、 狭い登山道。傾斜はほぼ無い(右) 
狭いところを登る。すれ違いは厳しい 

この付近も石が登山道を塞いでいるようにある(左)、 この付近も狭い。右カーブ(右) 

登山道脇に巨石(左)、 狭いが平らな道(右) 
B−06地点。女体山頂まで900m、筑波山神社から1770m 
この付近も傾斜はほとんど無いが、乗り越える場所は多い 

平らな緩い左カーブ(左)、 石と樹木で盛りあがった場所を乗り越える(右) 

この付近もほとんど傾斜は無い(左)、 苔むした石がたくさん転がってる(右) 

この付近から傾斜が急になる(左)、 同じく急傾斜になった登山道(右) 

樹木と石で登山道が塞がれている場所。隙間を通る(左)、 この付近も傾斜はかなり急(右) 

遠くの空間が聖天神社分岐(左)、聖天神社分岐手前(右) 
聖天神社前分岐(弁慶茶屋跡)。休憩スペースとしてベンチが置かれている。右側からおたつ石コースが合流。正面が山頂方面 

聖天神社前分岐過ぎてすぐ。正面に弁慶七戻りがある(左)、 弁慶七戻り手前。一番近くにあった巨樹が台風で折れ、現在は切り株を残すのみ(右) 
弁慶七戻り。こちら側より過ぎてから振り返ったほうが怖い 
弁慶七戻りのなか 

弁慶七戻り過ぎ。ここから振り返ってみた姿がパンフレットなどに掲載がある弁慶七戻り(左)、 ここから急傾斜。岩場を越えていく。ここから巨石が連続する(右) 
右側に巨石。足元も大きな石が転がっている場所を進む 

正面が高天原(左)、 高天原脇の段差。右側からか、左にある小さな鉄製の階段を登る(右) 
母の胎内潜り前 

母の胎内潜り前から山頂方面を望む(左)、 この付近はほぼ平ら(右) 

正面にあるのが陰陽石(左)、 大きな石の間を進む(右) 
B−07地点。女体山頂まで600m、つつじケ丘から1140m、筑波山神社から2070m 
急な上り。道幅も狭く、鎖場になっている 

大きな石の段差を乗り越えていく(左)、 この付近は登山道にも大きな石の上(右) 
道幅が狭くなっている場所も 

ここも大きな石の段差(左)、 手前に国割石(右) 

下り、この先に出船入船(左)、 部分的に平らな土の道(右) 

右に裏面大黒(左)、 ここを上りきると渡神社(右) 
渡神社前 

ここから少し下り(左)、 同じく下り(右) 
この付近は平らな道が続く 

同じく平らな道(左)、 正面にあるのが北斗岩(右) 

北斗岩。右側から先に進む。北斗岩の下も通れる。左にあるのは小原木神社(左)、 北斗岩から先を望む(右) 

急な岩場が始まる(左)、 足場が悪いところも多い(右) 

ここを上りきると平らな場所に出る(左)、 この先は少し平らなところが続く(右) 
B−08地点。女体山頂まで300m、つつじケ丘から1440m、筑波山神社から2370m。 この先、70〜80mは、アップダウンはあるが標高的にはほぼ平らな場所を進む 

直線の上り。傾斜はきつくない(左)、 石の道を乗り越える(右) 

短い木道(左)、 少しの区間平らな場所(右) 

この付近もほぼ傾斜は無い(左)、 再び短い木道(右) 

木道を過ぎると短いが平らな道(左)、 ここから急な上りがスタート(右) 

急な斜面、階段の幅は広い(左)、急傾斜右カーブ(右) 
全面石のみ。この辺から登山道上に石ばかりのところが多くなる 
この付近で標高は約800m 
頂上まで200m地点。つつじケ丘から1.2km、筑波山神社から2.5km。 左に入ると屏風岩。その前に安座常神社が祀られている 

頂上付近はかなり狭い場所も多い(左)、 最後の平らな場所。ここを過ぎると岩場のみ。左手に大仏岩(右) 

ここから急な岩場が続く(左)、 道も左右に細かく曲がる。ここは左へ(右) 
自然石だけの階段 

正面を左へ(左)、今度は正面を右へ(右) 
木の手すりのところを登る 
木の手すりで保護されている 

巨石を越えていく(左)、中央の岩を避けさらに左へ(右) 
急に狭くなる登山道 

この付近では、岩の間を抜けていく道になる(左)、 頂上が近づくにつれ大きな岩が目立つ(右) 

岩が渓流の河床のように広がる(左)、若干開けた場所(右) 

左から大きな岩が張り出す(左)、 最後の上り。かなり急な岩場(右) 
一番最後は鎖もある急傾斜 
白雲橋コース終点。左へ行くと頂上だが、順路は右。一度若干降りてから女体山本殿を経て頂上へ 

弁慶七戻り(左)、北斗岩(右) 

登山道終盤の岩だらけの上り(左)、弁慶七戻り手前から下山方向を望む(右)
copyright © 2007-2025 つくば新聞 by tsukubapress.com all rights reserved.
|